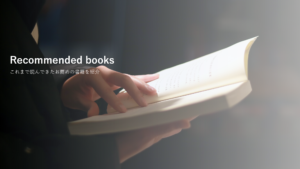
※本ブログはアフィリエイト広告を利用しています
これまで読んできた中で個人的に勉強になった書籍をカテゴリー別に紹介しています。
それぞれの筋肉のイラストが別々で表示されており、筋の付着部が分かりやすいです。
また、各筋の英語表記が記されたページも掲載されており、英語で筋肉の名前を覚えたい人にとってはいいかもしれません。
最後のページ近くに掲載されてある『筋肉の名前、起始停止、支配神経、作用がまとめられた表』がコンパクトにまとまっており、上手く活用すれば効率よく暗記することが出来るでしょう。
この本のココが特徴!
- 各筋肉のイラストが分かれて掲載されていて、起始停止が分かりやすい
- 各筋の英語表記も記載されている
運動学の専門書といった内容で、人間の身体の動きの仕組みについてこれでもかってくらい詳しく書かれています。
※運動学:解剖学、生理学そしてバイオメカニクスを基礎として、複雑で個別性の高い人間の運動を研究する学問(本書より抜粋)
理学療法士向けの専門書といった感じですが、トレーニング指導にも生かせる箇所が多く、ATやS&Cの方にもお勧めできます。
前半では、生理学やバイオメカニクスの基礎的内容がまとめられており、たまに読み直すことで網羅的に復習することもできます。
後半では、上肢、体軸骨格、下肢など各身体ごとの運動学が説明されていて、それぞれの身体部位で重要となる運動学を学ぶことができます。
ボリュームが凄いので、最初から読むというより気になった箇所を読んでいくという読み方がいいかもしれません。
値は張りますが、機能解剖学やバイオメカニクスの知識を基にしたトレーニングメニューを作成する際のヒントが得られるかもしれません。
この本のココが特徴!
- 前半では生理学とバイオメカニクスの基本的内容がまとめられている
- 後半では各身体部位で重要になる運動学がまとめられている
解剖学的な筋の構造や配置から、スポーツ場面でみられる動作を行うときに筋はどのように働くのかを解説しています。
「人体の△△のような特徴を踏まえると、エクササイズも〇〇を意識するといいよね」
といった形で、項目によっては解剖学的な特徴を踏まえたエクササイズの例なども紹介されています。
この書籍で紹介された箇所を読み込むことで、トレーニング指導者はもちろん、治療者のような方にとっても解剖学の基本に則ったエクササイズを
「なぜそのエクササイズ方法が良いのか?」
に対しての深い理解を持って処方することができるようになると思います。
また、その解剖学的理屈を自分の中で持っておくと、載ってるエクササイズに限らず、自らエクササイズの幅を広げることができると思います。
多少専門用語が多いため初学者にとってはややハードルが高めですが、各項目文章量はそこまで多くないので、何度も読み直して理解を深めやすいかと思います。
筆者の体験談なども盛り込まれていて、読み物としても非常に面白いです。
個人的にかなりお気に入りの書籍です!
この本のココが特徴!
- 基本的な機能解剖学の知識から、解剖学的な観点から理にかなったエクササイズやコンディショニング方法を学ぶことができる
- 筆者の体験談などを基に書かれており、読み物としても面白い
「アスリートのための解剖学」同様、エビデンスはもちろん、解剖学的な構造から人体構造の役割について解説しています。
こちらはアドバンス編ということで、先ほどよりも少し内容としては難しいものになっています。
しかし、文章内のイラストが非常に見やすく、文書の情景がイメージしやすいので理解はしやすいかもしれません。
詳細としては、「体幹の役割」「二関節筋の役割」のセクションが個人的に興味深かったです。
この本のココが特徴!
- 「アスリートのための解剖学」よりも内容は応用的であるものの、イラストが充実していてわかりやすい
- 「体幹の役割」や「二関節筋の役割」などについて解説が詳しくされている
解剖学の内容で確認したいことがあるときに利用している辞書的な本です。
リアルなイラストが使用されていて見やすいです。
一冊こういう系の本は持っておいて損はないと思います。
この本のココが特徴!
- 各筋の起始停止などを復習するときに使える
- イラストがリアルでイメージがしやすい
Big3の種目(スクワット、ベンチプレス、デッドリフト)に加え、バーベルショルダープレス、パワークリーンについて解剖学、バイオメカニクス的視点からフォーム解説をしている本になります。
これらの種目は高重量を扱う種目なだけに、適切なフォームを確実に身に着けておくべきであると思います。
こちらの本では、そのための安全でかつ効果的なフォームがどういったものかを理屈から理解して学ぶことが出来ます。
かなりオススメの本の1つです。
この本のココが特徴!
- スクワット、ベンチプレス、デッドリフト、バーベルショルダープレス、パワークリーンを中心に解剖学とバイオメカニクスの視点からみた適切なフォームを解説をしている
”入門”と書かれている通り、運動生理学に関する基本的内容が主な内容になります。
文章の読みやすさも抜群で、初学者であっても理解しやすいと思います。
生理学をほとんど学んだことのない後輩に貸したときも「わかりやすかった」といっていました。
これから生理学を学ぼうとしている人にオススメです。
この本のココが特徴!
- 運動生理学に関する基本的な内容が非常にわかりやすい言葉と図で説明されている
- 各章の最後にある『要約』もまとまってわかりやすい
こちらの書籍はATP-CP系、解糖系、酸化系を中心に運動中にどのようにしてエネルギーが利用され、再合成されるかを解説しています。
大きな特徴としては、ただ単純に解説するのではなく、実際のスポーツ現場でのシチュエーションを例に挙げて解説し、
難しい言葉はあまり使われておらず、一般の方でも理解できるような内容になっています。
また、よく巷で言われるような噂についても専門家の立場からその真偽を解説してくれています。
例えば、
「脂肪は運動開始から20分経過しないと使われないっていうのはホント?」
「俗にいう無酸素運動をしている時は酸素は使われていないの?」
「乳酸が疲労の影響と言われるけど、それは本当なのか?」
そんな疑問に対して、非常に専門的にかつわかりやすく解説されています。
内容としては前半に「基本編」があり、エネルギー代謝に関する基本的知識をおさらいしています。
そして後半には「実践編」と題して、実際のスポーツ現場を想定してどのようなトレーニングが必要になるかを解説しています。
個人的には初学者からすでに理解が深い方であっても大変勉強になる書籍だと思います。
かなりオススメの書籍です!
この本のココが特徴!
- エネルギー供給系が運動中にどのように利用されているかをわかりやすい文章で解説している。
- 基本編から詳しく解説しているため、初学者の方でも理解しやすい。
- 実際のスポーツ現場を想定した解説になっているのでイメージが掴めやすい
こちらは先ほどの「エネルギー代謝を活かしたスポーツトレーニング」よりも乳酸にフォーカスして、運動中に乳酸がどのように生成されて利用されているかを解説しています。
「エネルギー代謝を活かしたスポーツトレーニング」と重なる内容もありますが、どちらも非常にわかりやすく解説されています。
個人的には「エネルギー代謝を活かしたスポーツトレーニング」を読んでおくと基本的なことを満遍なく学ぶことができると感じていますが、
もっと乳酸に特化した内容(乳酸トランスポーターの話や血中乳酸濃度の捉え方)も深く勉強したいという方にとってはこちらの書籍もオススメできます!
この血中乳酸濃度の捉え方のパートを読むと、どうして乳酸が疲労の主な原因ではないのかということが理解しやすいかと思います。
単純に読み物としてかなり面白いです。
価格も手頃で読みやすいので、気になる方はどちらも手元にあると良いかもしれません。
この本のココが特徴!
- 「エネルギー代謝を活かしたスポーツトレーニング」と内容が重なるところもあるが、より乳酸に特化した内容が組み込まれている。
こちらは持久系トレーニングを実施するとどのような分子メカニズムでミトコンドリアの量や機能が改善するか等を非常に専門的に解説しています。
先ほど紹介した「エネルギー代謝を活かしたスポーツトレーニング」と「乳酸を活かしたスポーツトレーニング」と比較してかなり専門的に書かれており、マニアックな内容も含まれています。
自分はHIITでどのようなミトコンドリアの適応が生じるのかについての理解を深めるために読みましたが、非常に勉強になりました。
各パートは、様々な大学で教鞭を執る先生方が解説しており、徹底的に深掘りされています。参考文献も豊富です。
ミトコンドリアに関わる論文を読まれている方が理解を深めるためには、非常にタメになる書籍かと思います。
この本のココが特徴!
- ミトコンドリアに関して、各大学の先生方が豊富な参考文献とともに詳細に解説している。
- 一般の方が読むには少し専門性が高いかもしれない。論文などを読まれている方が知識を深めるためには非常に勉強になる一冊。
NSCAの資格(NSCA-CPTやCSCS)を取得するために必要になってきます。
NSCAの資格を保有している人は皆さんこの教科書を勉強していることかと思いますので、
この一冊を勉強することで同業者の方と最低限の共通言語で会話することができるようになるかと思います。
S&Cを始めて学ぶ人はまずこの本からといったところでしょうか
この本のココが特徴!
- NSCAの資格を取得するのに必須の教科書
- 幅広い分野に関する基礎知識が掲載されている
こちらは長期的なプログラムデザインの際に大切になってくるテーパリングについて解説された本になります。
日本語で書かれた書籍の中で、ここまでテーパリングにテーマを絞って解説しているものは他にないかと思います。
具体的な失敗例や活用例も紹介されていてイメージがしやすく読みやすいです。
S&Cコーチはもちろん、部活動の競技指導をされている方にもお勧めできます。
この本のココが特徴!
- フィットネス-疲労理論を用いたテーパリングの方法について詳しく書かれている
- 具体的な失敗例や活用例が書かれていて、イメージがしやすく読みやすい
こちらの書籍の”はじめに”でも書かれていますが、スポーツ科学という分野は比較的若い分野であり、
科学的根拠に基づくトレーニング指導が大事と言われていながらも、エビデンスをベースとして書かれたスポーツ科学に関連する書籍というのもあまり出回っていないというのが実情かと思います。
そのような中、こちらの書籍ではトレーニング指導を行う上で重要なトピックについて、各分野の専門家がエビデンスベースに解説しており、
「科学的根拠に基づくトレーニング指導」を実現させるための手助けとなる書籍になっています。
普段論文を読む習慣がない方にとっても、わかりやすい内容になっており、
学生を含めた多くのトレーニング指導者にとって手元に置いておきたい参考書かと思います。
この本のココが特徴!
- 科学的根拠に基づくトレーニング指導を実現するための手助けとなる書籍
- 各分野の専門家がエビデンスベースでわかりやすく解説している。
- 専門家の視点からどのように現場へ活かしていくかが解説されている。









